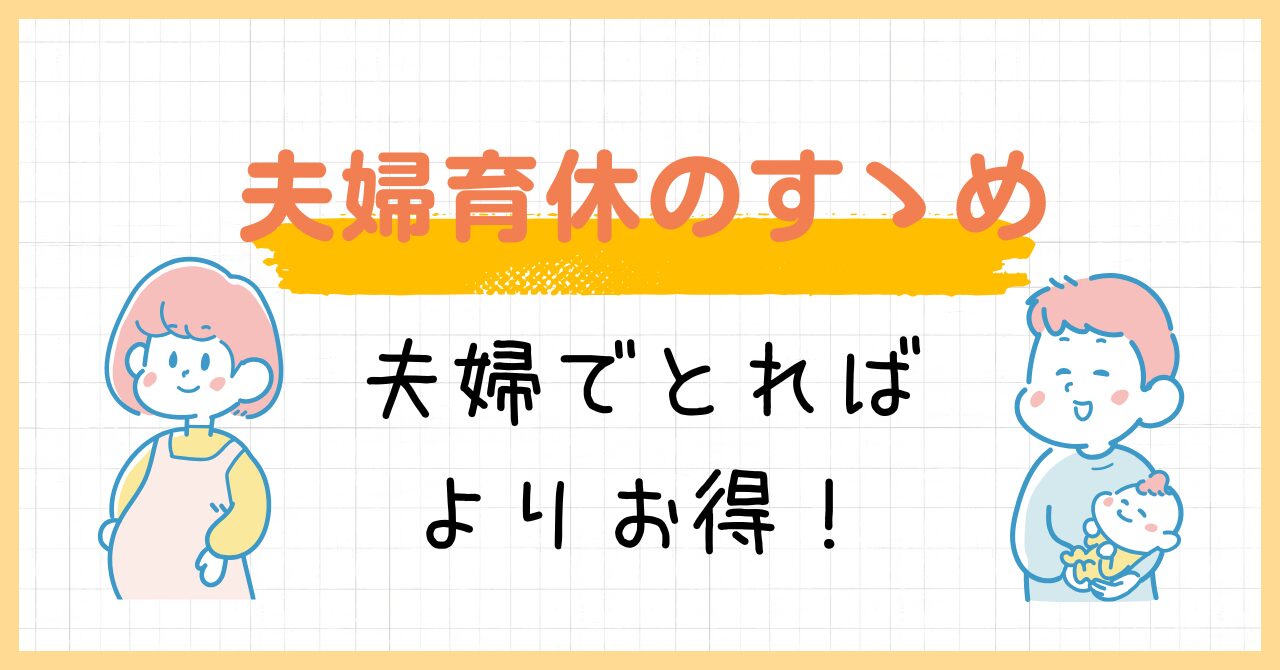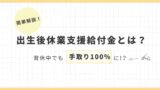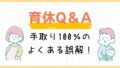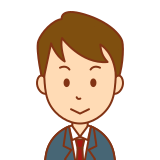
産後は大変だから、夫婦で育休を取ろう!職場に掛け合ってみるよ。
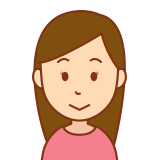
嬉しいけど、パパまで休んでお金は足りるかな。
実は手当で損したりはしないかな?
育休についての悩みは「仕事とのバランス」と「お金」についてがほとんどです。
新たな命を迎え、家族の時間を大切にしたい大事な時期!
しかし実際には、お金の不安で夫婦育休を断念している家庭も少なくないでしょう。
結論、基本的に手当に関して夫婦育休で損することはありません!
夫婦育休限定の給付や制度により、「手当ての増額」があるからです。
とり方次第では、一人育休よりも手取りを増やせる可能性もあります!
この記事では、「夫婦で育休=損」という誤解を解き、夫婦育休だからこそ使える2つのお得な制度や、手当を最大限もらうためのコツをわかりやすく解説します。
- 【夫婦育休限定】手当を手取り100%にする方法
- 【夫婦育休限定】手当の支給期間を2か月延長する方法
- 社会保険料が免除される、おすすめの育休取得のタイミング
これから育休を検討しているご家庭や、育休をどのように分担するか悩んでいる方にとって、きっと役立つ内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
手当に直結!夫婦育休の2つのお得な制度
夫婦で育休を取得すると、ただ家事や育児を分担しやすくなるだけでなく、「お金の面でも得をする」制度が用意されています。
制度を正しく活用することで、「一人育休よりも手取りが増える」という点をご理解ください!
【夫婦育休限定】手当てが100%に増額!
一つ目は、「出生後休業給付支援金」という制度です。
これは、一定期間中に夫婦で育休を取得することにより、最大28日間、通常の育休手当に13%の追加支給が受けられる制度です。
共働きの場合は、原則夫婦で取得しなければ活用できない「夫婦育休限定」の制度です。
67%(育児休業給付金)+13%(出生後休業支援給付金)=80%
※社会保険料の免除を加味して、手取りベースで100%
つまり、夫婦で育休を取得することで、収入としては育休を取っていない状態と同じ水準を維持できるわけです。
一人育休の場合は67%支給となってしまうため、これは夫婦育休限定の超お得制度といえるでしょう。
給付要件や支給期間については細かいので、こちらの記事を参照ください。
【夫婦育休限定】手当の支給期間が2か月延長!
2つ目は、「パパ・ママ育休プラス(パパママ+)」という制度です。
通常、育休手当は原則子どもが1歳になるまでの支給ですが、夫婦が育休を交互に取得するなどの条件を満たすと、最大で2か月間延長(=1歳2か月まで)される場合があります。
この延長は、単に夫婦どちらかが休める期間が長くなるというだけでなく、育児休業給付金の受給期間も延びるという点で、家計にとって大きなプラスです。
- 夫婦で仕事も家庭もバランスよく大切にしたい方
- 子どもが2月・3月生まれで、保育園を4月入園にしたい方
夫婦育休を「損」せずに取るためコツ2選
次は、制度そのものではなく、それらを利用した「育休のとり方」について注目してしましょう。
社会保険等の仕組みを知ることで、夫婦育休を「損せず」最大限に活用するためのコツが見えてきます。
損しない育休のコツ①:社会保険料が免除になるとり方とは
一つ目のポイントは、社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除を狙った育休のとり方です。
結論、育休は、月末を含んで取得することが重要です。
元々、1か月以上の育休取得が難しい場合は、当月中に14日以上を目指しましょう。
社会保険料の支払いに関する決まりは以下の通りです。
- 月の末日に事業場(会社等)に属している場合、場合に支払い義務が生じる
→月の末日に育休中であれば、社会保険料はかからない - 【特例】14日以上の育休取得した月は免除される
たとえば、今月末から翌月末まで育休をとれば、2か月分の保険料が免除されることも可能です。
- 例①:9月25日〜10月31日で育休を取得した場合
→ 9月・10月の社会保険料が免除 - 例②:9月29日~9月30日で育休を取得
→9月分の社会保険料のみ免除
※月末1日のみではダメ
月末に育休中であればよいので、例②のようにたった2日間育休を取得しただけでも1か月分の社会保険料を免除することができます。
これにより、収入の観点だけで言うと「働くより育休をとった方がお得」になるので驚きです。
損しない育休のコツ②:育休の交互取得で、手当の減額回避!
もう一つのポイントは、育休手当の支給率を高めに維持するとり方です。
夫婦同時に育休を取るよりも、交互に取得することで得られるメリットがあります。
「育児休業給付金」は、育休開始から最初の180日間(およそ6か月)に限り、支給率が67%と高く設定されており、その後は50%に下がってしまいます。
以下のような工夫をすることで、合計で約1年間も67%支給が続くことになり、同時取得よりも手取り額が多くなる可能性があります。
- 妻が出産直後から6か月取得 → 67%支給
- 妻の育休終了後に夫が6か月取得 → 夫も67%支給
この工夫の利点は、「パパ・ママ育休プラス(パパママ+)」を活用できる点です。
共働きで、仕事との両立を考えるうえでも、強力な選択肢の一つと言えるでしょう。
夫婦育休は損じゃない!手当も時間も手に入れよう
育休は「キャリアが止まる」「収入が減る」といったマイナスのイメージを持たれがちですが、制度を理解して活用すれば、家族の時間も手当もしっかり確保できる仕組みになっています。
まず、夫婦で育休を取得することで活用できる制度は次の通りです。
- 出生後休業支援給付金(13%)によって、実質手取り100%が可能に
- パパママ育休プラスにより、手当の支給期間が最大2か月延長
次に、損しない育休のとり方は以下の通りです。
- 社会保険料の免除タイミングを工夫すれば、手取りアップにもつながる
- 交互に取得すれば、手当の67%支給期間が伸ばせる
これらの制度を上手に活用すれば、育休期間中も「損するどころか、むしろ得する」と感じられるケースも多くあります。
前提として、育休をとる目的は「得をするため」ではなく「家族の時間を確保するため」だと思います。
出産のタイミングや人手が必要になるタイミングはご家庭によって様々です。
上記の方法を意識しすぎるのではなく、「1日ずらして使えそうなら使ってみる。」という感覚で向き合うのが適切な距離感といえるでしょう。
子どもの成長は一瞬で、今しかない時間。
夫婦で育休を取ることで、育児の負担を分け合えるだけでなく、お互いを理解し支え合う関係性を築くことができます。
「お金が心配…」とためらっていた方も、この記事でご紹介した制度を味方につけて、一歩踏み出してみてください。
育休=損、は誤解。
正しく知って、家族にとって一番良い選択をしていきましょう。